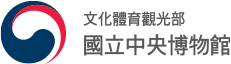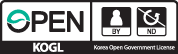国宝第83号半跏思惟像は、韓国古代仏教彫刻史研究の出発点であると同時に、6、7世紀東アジアの最も代表的な仏教彫刻品のひとつとしてよく知られています。またこの像は、日本・京都の広隆寺木造半跏思惟像と形状が酷似しており、韓国と日本の古代仏教彫刻交流研究において早くから大きな注目を集めている作品です。
一般的に半跏思惟像は、中国では、たいてい主な仏像に従属したり、一部分的な存在に過ぎなかったため、単独で礼拝対象として造像された例は珍しいですが、三国時代の百済では従属的な関係から抜け出し、独立的な造形性を獲得します。三国時代には半跏座特有の複雑な身体構造を無理なく消化し、中国の半跏思惟像から一貫して現れる姿勢の過程と単純化、同一な単位の皺が反復する図式性を克服し、半跏思惟像が大きく流行します。
精巧さと静かな微笑が漂わす崇高美

半跏思惟像は、左側の膝上に右足を乗せた、いわゆる半跏の姿勢に右の頬に右指を若干当てて、まるで思惟するような姿勢を取っています。このような形式の仏像は、人間の生老病死に悩み、瞑想にふけるシッダールタ太子の姿にもとづくもので、インドのガンダーラや中国南北朝時代の仏伝レリーフのなかでしばしば登場します。中国で半跏思惟像は、5~6世紀に主に作られ、「太子像」「思惟像」「龍樹像」などの名称で記録されています。韓国には6~7世紀に大きく流行し、一般的に弥勒(未来の仏)と見られます。韓国の半跏思惟像は、その後日本の飛鳥、白鳳時代半跏思惟像に影響を及ぼします。
韓国で半跏思惟像を弥勒菩薩として見る認識は、新羅でとくに盛行しましたが、新羅では転輪聖王思想の流行と合わせて、花郎を未来の救世主である弥勒の化身と考えるようになります。当時新羅に弥勒信仰が流行していたため、半跏思惟像が弥勒菩薩として作られたという見解が説得力を得て、このように呼ばれるようになりました。しかし半跏思惟像を弥勒菩薩と断定して呼ぶことは、文献的根拠が非常に弱く、「半跏思惟像」と呼ぶのが無難です。
国宝第83号半跏思惟像は、大きさ93.5㎝で金銅製半跏思惟像のなかでも、最も大きいだけでなく、最上の美しさを誇る作品です。単純ですが、バランスを取った身体、自然ながらも立体的に処理された衣文、明確に表現された目鼻口、精巧で完璧な鋳造技術、さらに顔の穏やかな微笑は宗教の礼拝対象が与える崇高美を加えています。
頭には3つの半円が続いた三山冠または蓮花冠を被っています。冠の表面に何の装飾も表現されておらず、たいへん単純ながらも強烈な印象を漂わせていますが、このような形式の宝冠は、インドや中国の菩薩像ではほとんど見られないものです。豊満な顔に眉毛の線は長く弧を描いて鼻の線に繋がりますが、小さいながらも長く描写された目は、端がやや上がってやや鋭い印象を漂わせています。しかしこの印象を抑えるのように端正につぐんだ口端が若干吊り上がって、微笑をうかべる姿は神秘感さえ与えています。
裸の上半身は胸の筋肉が若干浮き立って、腰はくびれています。右側の顔に当てている指は、動きを表現して律動感があり、これと対称に上に乗せた右腕の足は目一杯力を加えて曲げた姿が生き生きとした印象を加えています。半跏思惟像の制作においてとくに難しいのは右腕の処理です。右腕は膝で曲げて頬に再び触れなければならないので、長く表現されることになっています。しかし国宝83号像は、右側の膝を上に僅かに上げて、肘を支え、その腕もまた斜めにわずかに曲げた指で頬に触れており、たいへん緻密な力学的構成を見せており、このような有機的な関係は、わずかにもたげた顔と上半身に連なります。

出土地が不明確で新羅の作、あるいは百済の作と見る見解に分かれる
日帝強占期に発見されたこの像は、出土地が正確でありません。これにより新羅の作、あるいは百済の作と見る見解で紛糾していますが、今まで国宝第83号像は、日本の広隆寺木造半跏思惟像の制作地を根拠に、新羅の作という主張が最も説得力を得ています。両像は三面冠の宝冠、胸と腰の処理、膝下の衣文と椅子両脇に垂らされた腰帯の装身具などがたいへん酷似して、早くから両国の古代仏教彫刻交流において注目を受けてきました。広隆寺の木造半跏思惟像は、当時日本の木造仏のほとんどがクス製やカヤ製であったのに対して、韓国の慶尚道一帯で多く自生しているアカマツで作られており、制作方法においても身体の各部分を複数の彫刻に分けたのち、組み合わせた一般的な方法とは異なり、木の塊から像を彫り出しています。また『日本書紀』623年条に新羅から持ち込んだ仏像を広隆寺に奉納したという記録があり、この仏像を木造半跏思惟像と推定しています。しかし広隆寺像が国宝83号像に比べて静的な印象が強く、互いに異なる造形感覚を漂わせる点も提起されており、美術史的にも調和と均衡がとれた形と優雅かつ洗練された彫刻技術から推して百済の作と見るのが妥当であるという見解も共に提示されています。このように制作地についての問題は、今後新たな資料の発掘と共に引き続き解決すべき課題と言えます。